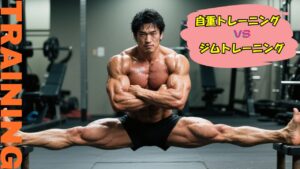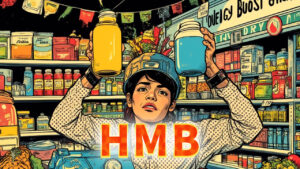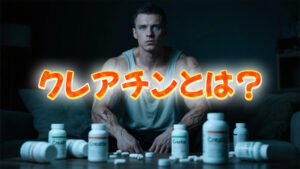【完全保存版】プロテインの選び方と効果|ホエイ・ソイ・ダイエット用・即飲みタイプまで徹底解説
「筋トレを始めたけど、どのプロテインを選べばいいのかわからない…」
「ホエイ?ソイ?結局どれが効果的なの?」
「最近コンビニでも買える“その場で飲めるプロテイン”って、普通のプロテインと何が違うの?」
こんな疑問を抱えていませんか?
プロテインは、トレーニング効果を最大化し、理想の体を作るために欠かせない栄養源です。しかし、種類が多く、初心者にとっては何を選ぶべきか迷ってしまいがちです。
さらに近年は、筋トレ用だけでなく、ダイエット専用プロテイン・即飲みタイプ・スープ系のたんぱく質食品・ドラッグストアのレトルトヘルシー食材まで、選択肢が大きく広がっています。
この記事では、以下のポイントを徹底解説します。
- プロテインの基本知識(ホエイ・ソイの違い、含有率100%や80%の意味)
- 筋トレ用プロテインとダイエット用プロテインの使い分け
- コンビニやジムで買える即飲みタイプの特徴
- スープやレトルト食品で手軽にたんぱく質を補う方法
初心者にもわかりやすく、科学的根拠を踏まえて解説します。
最後まで読むことで、あなたに最適なプロテインが見つかり、効率的に体づくりを進められるはずです。
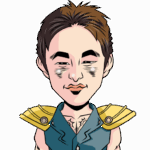 制作者 hiroyuki
制作者 hiroyuki第1章 プロテインとは?基礎から理解する
プロテイン(Protein)は、たんぱく質を英語で表した言葉です。
筋肉だけでなく、髪・爪・ホルモン・免疫細胞など、私たちの体の大部分はたんぱく質でできています。
筋トレやダイエットでは特に、筋肉の合成と維持に十分なたんぱく質が必要です。
しかし、食事だけで必要量を摂取するのは難しく、そこで登場するのがサプリメントとしてのプロテインです。
一般的に、成人が筋トレをしていない場合でも体重1kgあたり約1.0gのたんぱく質が必要です。
筋トレをしている人は、体重1kgあたり1.5〜2.0gが推奨されます。
この量を肉や魚だけで摂るのは大変なので、効率よく摂取できるプロテインが重要になります。
第2章 ホエイプロテインとソイプロテインの違い
2-1 ホエイプロテインとは
ホエイ(Whey)は牛乳から作られる乳清たんぱくです。
特徴は以下の通りです。
- 吸収が早い(1〜2時間で吸収)
- 筋肉の回復や成長を促進しやすい
- 運動直後に最適
ホエイプロテインは、筋肉を効率よく増やしたい人、ハードなトレーニングを行う人に向いています。
2-2 ソイプロテインとは
ソイ(Soy)は大豆由来の植物性たんぱく質です。
特徴は以下の通りです。
- 吸収がゆっくり(4〜6時間かけて吸収)
- 満腹感が持続しやすく、食欲を抑える効果が期待できる
- 女性ホルモン様の作用を持つイソフラボンを含むため、美容にも良いとされる
ソイプロテインは、ダイエットを目的とする人、健康維持を重視する人におすすめです。
2-3 含有率100%・80%の意味
プロテインのパッケージに「ホエイ100%」や「ソイ80%」と書かれているのを見たことがあるでしょう。
- 100% → 主成分がそのプロテインのみで作られている
- 80% → 主成分がそのプロテインだが、残りはビタミン・ミネラル・糖質などが配合されている
筋トレ目的なら、純度の高いホエイ100%が筋肉合成に有利です。
ダイエット目的なら、糖質や食物繊維を含むソイ80%前後のブレンドタイプも選択肢になります。
第3章 筋トレ用とダイエット用プロテインの違い
3-1 筋トレ用プロテイン
筋トレ用は、筋肉の合成を最優先に作られています。
特徴は以下の通りです。
- ホエイたんぱく質が主体
- 吸収スピードが速い
- 糖質や脂質が少ない
- トレーニング後に飲むと効果的
有名ブランド例:ゴールドスタンダード、ビーレジェンド、DNSなど
3-2 ダイエット用プロテイン
ダイエット用は、カロリーを抑えつつ満腹感を維持できるよう設計されています。
特徴は以下の通りです。
- ソイたんぱく質主体
- 食物繊維・ビタミン・ミネラルを含む
- カロリーや糖質が低め
- 置き換え食として利用できる
有名ブランド例:ラクシブプロテイン、ザバス シェイプ&ビューティーなど
第4章 その場ですぐ飲める即飲みタイプのプロテイン
近年はコンビニやドラッグストアで手軽に買える、紙パックやボトル入りの即飲みプロテインが人気です。
特徴:
- シェイカー不要、持ち運びに便利
- フレーバーの種類が豊富(バニラ、チョコ、カフェオレ、いちごミルクなど)
- 吸収スピードはホエイ主体なので筋トレ後にも使える
- 1本あたり15〜25gのたんぱく質を含む商品が多い
主な商品例:ザバスミルクプロテイン、inPROTEINドリンク、マイプロテインRTDなど
第5章 スープやレトルトでたんぱく質を補う新習慣
トレーニーやダイエッターの間で注目されているのが、高たんぱくスープやレトルトヘルシー食品です。
例えば薬局チェーンの「サンロード」やコンビニで購入できる、
- 高たんぱく味噌汁
- たんぱく質入りスープ(コーンスープ、トマトスープなど)
- レトルトの鶏むね肉入りスープカレー
これらは1食でたんぱく質10〜20g前後を補給できるうえ、低カロリー・低脂質でダイエットに適しています。
食事の一部として取り入れることで、無理なくたんぱく質量を増やせます。
第6章 プロテインを活用するポイント
6-1 タイミング
- トレーニング後30分以内(ゴールデンタイム)
- 朝食時(睡眠後はたんぱく質が不足している)
- 間食や夜食に(食事で足りない場合)
6-2 摂取量の目安
- 筋トレをしている人:体重×1.5〜2.0g/日
- ダイエット目的:1日60〜80gを目安に、2〜3回に分けて摂取
第7章 よくある疑問Q&A
Q1. プロテインは飲みすぎると太る?
→ 過剰摂取すればカロリー過多になり太ります。ただし、必要量を守れば太りません。
Q2. 食事だけではダメなの?
→ 食事だけで十分なたんぱく質を摂れれば問題ありませんが、現実的には難しいためプロテインが便利です。
Q3. 即飲みタイプは粉より効果が劣る?
→ 成分はほぼ同じなので、目的に応じて使い分けてOKです。
第8章 プロテインを飲むと太りやすい?【誤解を解消】
「プロテインを飲むと太る」という話を耳にしたことはありませんか?
実はこれは半分正しく、半分誤解です。結論から言えば、プロテインそのものが太る原因ではなく、摂取カロリーのバランス次第です。
8-1 プロテインは“魔法のドリンク”ではない
プロテインはあくまでたんぱく質を効率よく補給する栄養補助食品であり、それ自体に脂肪を増やす作用はありません。
しかし、次の点を理解しておくことが重要です。
- プロテイン1杯(20〜25gのたんぱく質)=約100〜150kcal
- 味付きプロテイン(チョコ・ストロベリーなど)は糖質が5〜10g前後含まれる
- 何も考えずに1日に何杯も飲めば、余分なカロリー摂取になる
つまり、消費カロリー<摂取カロリーの状態になれば、たとえプロテインでも体脂肪として蓄えられます。
8-2 筋トレ中は太るより“引き締まる”
筋トレをしている場合は、プロテインは主に筋肉の合成に使われます。
たんぱく質は筋肉の修復・成長に必要なため、余分に摂っても筋肉量の増加に役立ちやすく、太る心配は少ないのです。
- 筋肉量が増える → 基礎代謝が上がる → 太りにくい体へ
- 運動後に飲むことで、脂肪ではなく筋肉合成に優先的に利用される
このため、トレーニングを行っている人にとってはプロテインは太るどころか、理想の体づくりをサポートします。
8-3 ダイエット中は摂取量に注意
一方で、運動をほとんどしないのに高カロリーなプロテインを頻繁に飲むと、カロリーオーバーになる可能性があります。
特に注意すべきは次のケースです。
- 食事は普通に摂っている+1日2〜3杯のプロテインを追加
- お菓子感覚で甘いプロテインドリンクやバーを間食に取り入れてしまう
- 消費エネルギーが少ないのに、高たんぱく・高カロリーを摂取している
この場合は、筋肉ではなく余剰分が脂肪として蓄積される可能性があります。
8-4 太らないためのポイント
プロテインを取り入れる際は、次のポイントを守れば安心です。
- 総摂取カロリーを把握する
1日の消費カロリーを上回らないように注意しましょう。 - 運動量に合わせて摂取する
筋トレや有酸素運動をしていない日は、必要以上に飲む必要はありません。 - 食事と置き換える活用法
ダイエット中は、間食ではなく朝食や軽食をプロテインに置き換えることでカロリーを抑えつつたんぱく質を確保できます。 - 低糖質・低脂質のプロテインを選ぶ
フレーバー付きでも、糖質が少ないもの(1杯あたり糖質5g以下)を選ぶと安心です。
- プロテインは飲んだから太るわけではない
- 太る原因は「摂取カロリーの過剰」
- 適量を運動と組み合わせて摂取すれば、むしろ引き締まった体づくりをサポートする
プロテインを上手に活用することで、筋肉を増やしながら脂肪を減らす理想的なボディメイクが可能になります。
第9章 コンビニのプロテインは高い?太りやすい?粉末タイプ3kgとどちらが良いか
最近では、コンビニでも手軽に買える即飲みタイプのプロテインドリンクが人気です。
しかし、筋トレを本格的に行う人の間では、「コンビニのプロテインは割高では?」
**「飲みやすいけれど太りやすい?」**という疑問が多く聞かれます。
ここでは、コンビニの即飲みタイプと大容量の粉末タイプ(3kg)を比較し、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
9-1 コンビニの即飲みプロテインの特徴
近年は、ザバスミルクプロテインやinPROTEINドリンクなど、コンビニやドラッグストアで買える商品が充実しています。
メリット
- シェイカー不要で、その場ですぐ飲める
- 味が飲みやすく、フレーバーの種類が豊富(ココア・バナナ・カフェオレなど)
- トレーニング直後にすぐ補給できる
- 1本あたり15〜25gのたんぱく質を摂取できる
- 冷えていて飲みやすいので初心者も続けやすい
デメリット
- コストが高い(1本あたり約150〜220円)
- 糖質が含まれている商品もあり、ダイエット中は注意が必要
- 飲み続けるとランニングコストがかさむ
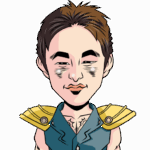
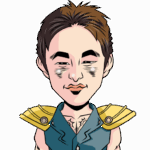
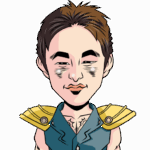
1日2本(約40gたんぱく質)を30日飲むと、
200円×2本×30日=12,000円/月がかかります。
9-2 粉末タイプ(3kg)の特徴
ジムユーザーや本格的なボディメイクを目指す人の多くは、コスパの良い粉末タイプを選びます。
メリット
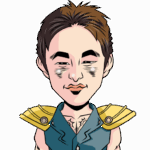
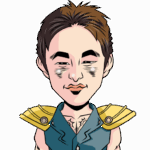
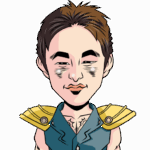
圧倒的にコストが安い
例:3kg(約100食分)で8,000円前後 → 1食あたり約80円
- フレーバーの種類が多い(バニラ・チョコ・抹茶・クッキークリームなど)
- 高たんぱく&低脂質・低糖質の製品が多く、体づくりに最適
- 長期間ストックできる
デメリット
- シェイカーと水や牛乳が必要
- 外出先で飲むにはやや不便
- 初心者には味にクセを感じる場合がある
9-3 太りやすさの比較
「コンビニのプロテインは太る」という声を聞きますが、結論としては飲み方と総摂取カロリー次第です。
- コンビニドリンクは糖質が5〜10g含まれることが多く、甘い味わいのため飲みすぎには注意
- 粉末タイプは、糖質がほとんど含まれない製品(1杯1〜3g)も多いため、カロリーをコントロールしやすい
- ダイエット中は低糖質の粉末タイプが有利
- 筋トレ後に素早く栄養補給したいときはコンビニの即飲みも便利
重要なのは、どちらを選んでも総摂取カロリーが消費カロリーを超えなければ太らないという点です。
9-4 コストと効果の比較表
| 項目 | コンビニ即飲みタイプ | 粉末タイプ(3kg) |
|---|---|---|
| 価格 | 1本150〜220円(たんぱく質15〜25g) | 1杯約80〜100円(たんぱく質20〜25g) |
| 継続コスト(30日換算) | 約9,000〜13,000円 | 約3,000〜4,000円 |
| 手軽さ | シェイカー不要ですぐ飲める | 水やシェイカーが必要 |
| 糖質量 | やや多め(5〜10g前後) | 低糖質製品が豊富(1〜3g) |
| 筋トレ直後の補給 | 非常に便利 | 自宅なら問題なし |
| ダイエットのしやすさ | 飲みやすいがカロリー管理が必要 | 低糖質なので管理しやすい |
9-5どちらを選ぶべきか?
- 初心者・外出が多い人 → コンビニの即飲みタイプ
「まずは続ける習慣をつけたい」「外出先でも手軽に飲みたい」という人には、多少割高でもコンビニの即飲みタイプが続けやすい。 - 本格的に筋トレ・ダイエットをしたい人 → 粉末タイプ3kg
コスパ・栄養バランス・糖質管理の面で優れており、長期的な体づくりに向いている。
理想は、日常は粉末タイプを基本にし、外出時やトレーニング後の即補給にはコンビニの即飲みを活用するハイブリッドスタイルです。
こうすることでコストを抑えつつ、効率的な栄養補給が可能になります
まとめ
- プロテインは筋トレ・ダイエットに欠かせない栄養補助食品
- ホエイは筋肉重視、ソイはダイエットや美容向け
- 含有率100%は純度が高く、80%は栄養素を加えたブレンドタイプ
- 即飲みタイプやスープ・レトルト食品を活用すれば、より手軽に継続できる
- 重要なのは、目的に合ったタイプを選び、適切なタイミングで摂取すること
プロテインは単なるサプリではなく、ライフスタイルを支える強力なパートナーです。
正しい選び方と使い方を知れば、筋トレの成果を加速させ、健康的な体づくりをサポートしてくれます。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cca5eef.9defac0a.4cca5ef0.b3094969/?me_id=1384858&item_id=10000152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgrong%2Fcabinet%2F07429343%2Fcp_px5%2Fgrong-184_rp_250613.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d1842e8.c6610f7a.4d1842e9.631adfde/?me_id=1381763&item_id=10000629&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flibertylife%2Fcabinet%2F08071365%2F08071366%2F08685823%2Fimgrc0084565576.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d184189.9518c0b9.4d18418a.9ac103c5/?me_id=1419885&item_id=10000616&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fotodokestore-plus%2Fcabinet%2Fchoice%2Fimgrc0116874284.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d184050.b36f7115.4d184051.dfb15ea8/?me_id=1383220&item_id=10000324&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fajinomoto%2Fcabinet%2Fprd%2F75%2Fr4901001711475_2509.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d1846fc.44f74f21.4d1846fd.dcc00b21/?me_id=1235074&item_id=10160863&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpocket-cvs%2Fpoi5%2F4902888731426-2sm.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)