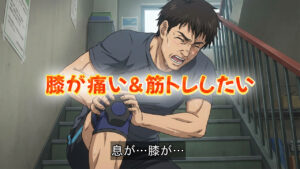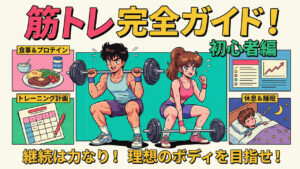筋トレすると体重が増える?どのくらい増えるのか解説
「ダイエットのために筋トレを始めたのに、体重が増えてしまった」「見た目は引き締まってきたのに、体重計の数字が減らない」――このような経験をした方は少なくないでしょう。筋トレと体重の関係は、多くの人が誤解しがちなテーマです。
実は、筋トレを始めると一時的、あるいは継続的に体重が増加することは珍しくありません。しかし、これは必ずしも悪いことではなく、むしろ体が良い方向に変化している証拠である場合が多いのです。体重という数字だけに囚われていると、せっかくの筋トレの効果を正しく評価できず、モチベーションの低下につながってしまうこともあります。
本記事では、身長170センチ、体重70キログラムの標準的な成人男性を基準として、筋トレによって体重がどのように変化するのか、その背景にあるメカニズムを科学的に解説します。筋肉と脂肪の密度の違い、体の水分量、カロリー収支、そして実際にどのくらいの期間でどれだけ体重が増えるのかを、具体的な数値とともに詳しく見ていきましょう。
この記事を読めば、体重計の数字に一喜一憂することなく、本当の意味での体の変化を理解し、より効果的なトレーニングを続けられるようになるはずです。
筋肉と脂肪の密度・重さの違い
筋肉と脂肪の密度・重さの違い
筋トレによる体重増加を理解する上で、最も重要なのが筋肉と脂肪の密度の違いです。多くの人が見落としがちですが、同じ体積でも筋肉と脂肪では重さが大きく異なります。
筋肉の密度は約1.1g/cm³(1立方センチメートルあたり1.1グラム)です。一方、脂肪の密度は約0.9g/cm³と、筋肉よりも約20%軽くなっています。つまり、同じ1リットル(1000cm³)の体積を比較すると、筋肉は約1100グラム、脂肪は約900グラムとなり、その差は約200グラムにもなります。
この密度の違いが、体重と見た目のギャップを生み出す主要因です。例えば、筋トレによって脂肪が1キログラム減少し、筋肉が1キログラム増加したとします。体重計上では変化がないように見えますが、実際には体積が大きく変化しています。
脂肪1キログラムの体積は約1111cm³(1000g ÷ 0.9g/cm³)ですが、筋肉1キログラムの体積は約909cm³(1000g ÷ 1.1g/cm³)となります。その差は約202cm³、つまり脂肪の方が約22%も体積が大きいのです。
身長170センチ、体重70キログラムの標準的な男性の場合、体脂肪率が平均的な18%程度だとすると、体脂肪量は約12.6キログラムとなります。仮にこのうちの2キログラムが筋肉に置き換わったとしても、体重は70キログラムのままですが、体積は約404cm³(約2.2リットルのペットボトル約0.2本分)も減少することになります。
これが、「体重は変わらないのに、見た目が引き締まった」という現象の正体です。筋肉は脂肪よりも密度が高く、同じ重さでもコンパクトなため、体重が同じでも体はより引き締まって見えるのです。
筋トレによる体重増加のメカニズム
筋トレを開始すると、体重が増加する理由はいくつかあります。それぞれのメカニズムを詳しく見ていきましょう。
1. 筋肉量の増加
最も直接的な原因が、筋肉量そのものの増加です。筋トレによって筋繊維が刺激を受けると、体はその刺激に適応するために筋肉を太く、強くしようとします。このプロセスを「筋肥大」と呼びます。
筋肥大は、筋トレによって筋繊維に微細な損傷が生じ、それを修復する過程でより強い筋肉が作られるという仕組みです。適切な栄養補給と休息を伴えば、筋肉は以前よりも太くなり、結果として体重が増加します。
2. 筋グリコーゲンと水分の貯蔵
筋トレを始めると、筋肉内に貯蔵されるグリコーゲン(糖質の貯蔵形態)の量が増加します。グリコーゲンは筋肉のエネルギー源として重要で、トレーニングを続けることで体はより多くのグリコーゲンを筋肉に蓄えられるようになります。
重要なのは、グリコーゲン1グラムを貯蔵する際に、約3〜4グラムの水分も一緒に貯蔵されるという点です。身長170センチ、体重70キログラムの男性の場合、筋肉量は約30〜35キログラム程度ですが、筋トレ開始前の筋グリコーゲン貯蔵量は約300〜400グラム程度です。
トレーニングを続けることでこの貯蔵量が500〜600グラムまで増加する可能性があります。グリコーゲンが200グラム増加すれば、それに伴う水分は600〜800グラムとなり、合計で800〜1000グラム、つまり約1キログラムの体重増加につながります。
3. 炎症反応と一時的な水分貯留
筋トレを始めたばかりの時期や、いつもより強度の高いトレーニングを行った後は、筋肉に炎症が起こります。これは筋肉の修復プロセスの一部で、炎症箇所には血液や体液が集まります。
この炎症反応による水分貯留は一時的なもので、数日から1週間程度で解消されますが、この期間は体重が1〜2キログラム増加することがあります。特に筋トレ初心者や、長期間のブランクの後にトレーニングを再開した場合に顕著です。
4. 食事量の増加
筋トレを行うと、消費カロリーが増加するだけでなく、食欲も増進します。また、筋肉を効率的に増やすためには十分な栄養摂取が必要という知識から、意識的に食事量を増やす人も多いでしょう。
摂取カロリーが消費カロリーを上回る「カロリーサープラス」の状態では、筋肉だけでなく脂肪も増加する可能性があります。適切なバランスを保てば筋肉の増加が主体となりますが、過剰なカロリー摂取は不要な脂肪の蓄積にもつながります。
人間の体の水分量と体重への影響
体重を構成する要素の中で、最も大きな割合を占めるのが水分です。成人男性の場合、体重の約60%が水分で構成されています。身長170センチ、体重70キログラムの男性では、約42キログラムが水分ということになります。
体内の水分は、大きく分けて以下のように分布しています:
細胞内液:体重の約40%(約28キログラム) 細胞の内部に存在する水分で、細胞の機能維持に不可欠です。筋肉細胞には特に多くの水分が含まれており、筋肉量が多い人ほど体内水分量も多くなります。
細胞外液:体重の約20%(約14キログラム)
- 血漿(血液の液体成分):約5%(約3.5キログラム)
- 間質液(細胞間の水分):約15%(約10.5キログラム)
筋トレが体内水分量に与える影響は以下の通りです:
1. 筋肉量増加に伴う水分増加
筋肉組織の約75%は水分で構成されています。つまり、純粋な筋肉(除脂肪筋肉組織)が1キログラム増加すると、そのうち約750グラムは水分、残りの約250グラムがタンパク質などの固形成分ということになります。
身長170センチ、体重70キログラムの男性が筋トレを1年間継続し、筋肉を3キログラム増やしたとすると、そのうち約2.25キログラムは水分の増加、約750グラムが実質的なタンパク質などの増加となります。
2. グリコーゲン貯蔵に伴う水分増加
前述の通り、グリコーゲン1グラムには3〜4グラムの水分が結合します。筋グリコーゲンが200グラム増加すれば、600〜800グラムの水分も増加し、合計で約1キログラムの体重増加につながります。
3. 日々の水分変動
体内の水分量は日々変動します。塩分摂取量、炭水化物摂取量、ホルモンバランス、気温、運動量などによって、1日で1〜2キログラム程度変動することは珍しくありません。
例えば、前日に塩分の多い食事を摂った場合、体は浸透圧を保つために水分を保持しようとし、一時的に体重が0.5〜1キログラム増加することがあります。また、女性の場合は月経周期によって最大2〜3キログラムの変動が見られることもあります。
このような水分による体重変動は、真の体組成の変化(筋肉や脂肪の増減)とは別物です。そのため、体重測定は同じ条件下(朝起きてトイレを済ませた後、食事前など)で行い、1週間や2週間の平均値を比較することが重要です。
筋肉量の増加ペースと現実的な体重増加
筋トレによってどのくらいのペースで筋肉が増えるかは、個人差が大きいものの、ある程度の目安があります。
筋トレ初心者の場合(最初の1年)
筋トレを始めたばかりの人は、最も速いペースで筋肉を増やすことができます。これは「初心者ボーナス」とも呼ばれ、体がトレーニング刺激に対して非常に敏感に反応する時期です。
適切なトレーニングと栄養管理を行った場合、初心者は月に0.5〜1キログラム程度の筋肉増加が期待できます。年間では6〜12キログラムの筋肉増加が可能ですが、これは理想的な条件下での話です。
身長170センチ、体重70キログラムの男性が、体脂肪率18%の状態から筋トレを始めたとしましょう。最初の1年で筋肉を8キログラム増やすことができれば、除脂肪体重は約8キログラム増加します。
しかし、筋肉組織の75%は水分なので、純粋なタンパク質などの固形成分の増加は約2キログラム、残りの約6キログラムは筋肉内の水分増加となります。さらにグリコーゲンと結合水分で約1キログラム増加すると、トータルで約9キログラムの体重増加が見込まれます。
同時に、適切な食事管理とトレーニングにより体脂肪が2キログラム減少したとすると、実際の体重増加は約7キログラムとなり、1年後の体重は77キログラムになる計算です。
トレーニング経験者の場合(2年目以降)
筋トレを1年以上継続している人は、筋肉増加のペースが徐々に遅くなります。2年目では月に0.25〜0.5キログラム、年間で3〜6キログラム程度の筋肉増加が現実的な目標となります。
3年目以降はさらにペースが落ち、年間2〜3キログラム程度の増加となり、5年目以降は年間1キログラム程度の増加を維持できれば上出来と言えるでしょう。
これは、筋肉量が遺伝的な限界値に近づくにつれて、新たな筋肉を増やすことが困難になるためです。体には筋肉量の上限があり、それに近づくほど成長は緩やかになります。
体重増加の内訳
筋トレによる体重増加の内訳を、身長170センチ、体重70キログラムの男性を例に、期間別に見てみましょう:
【筋トレ開始後1〜2週間】
- 筋グリコーゲンと結合水分:+0.8〜1.2kg
- 炎症による一時的な水分貯留:+0.5〜1.0kg
- 実質的な筋肉増加:+0.1〜0.2kg
- 合計体重増加:+1.4〜2.4kg
- 予想体重:71.4〜72.4kg
この時期の体重増加は主に水分によるもので、一時的です。
【筋トレ開始後1〜3ヶ月】
- 筋肉増加:+1.5〜3.0kg
- グリコーゲンと水分:+1.0kg(安定)
- 脂肪の変化:±0〜1.0kg(食事内容による)
- 合計体重増加:+2.5〜5.0kg
- 予想体重:72.5〜75.0kg
この時期から実質的な筋肉増加が始まります。
【筋トレ開始後6ヶ月】
- 筋肉増加:+4.0〜6.0kg
- グリコーゲンと水分:+1.0kg
- 脂肪の減少:-1.0〜2.0kg(適切な食事管理の場合)
- 合計体重増加:+3.0〜6.0kg
- 予想体重:73.0〜76.0kg
【筋トレ開始後1年】
- 筋肉増加:+6.0〜10.0kg
- グリコーゲンと水分:+1.0kg
- 脂肪の減少:-2.0〜3.0kg(適切な食事管理の場合)
- 合計体重増加:+4.0〜8.0kg
- 予想体重:74.0〜78.0kg
これらの数値はあくまで目安で、個人の遺伝的素質、トレーニングの質と量、栄養摂取、休息、ストレスレベルなどによって大きく変動します。
カロリーと筋肉増加の関係
筋肉を効率的に増やすには、適切なカロリー管理が不可欠です。筋肉の合成には、エネルギーと材料(主にタンパク質)の両方が必要だからです。
基礎代謝と消費カロリー
身長170センチ、体重70キログラム、30歳の男性の基礎代謝量は、ハリス・ベネディクト方程式を用いると以下のように計算できます:
基礎代謝量(BMR)= 88.362 + (13.397 × 70) + (4.799 × 170) – (5.677 × 30) = 88.362 + 937.79 + 815.83 – 170.31 = 約1,672 kcal/日
これに活動レベルを掛けた総消費カロリー(TDEE)は:
- ほとんど運動しない:1,672 × 1.2 = 約2,006 kcal/日
- 週3〜4回の筋トレ:1,672 × 1.55 = 約2,592 kcal/日
- 週5〜6回の筋トレ:1,672 × 1.725 = 約2,884 kcal/日
筋肉1キログラム増やすのに必要なカロリー
筋肉組織1キログラムを合成するには、理論上約1,700〜2,500 kcalの余剰カロリーが必要とされています。これは筋肉組織の約75%が水分であり、残りの約25%がタンパク質などの固形成分であることに由来します。
タンパク質1グラムは約4 kcalのエネルギーを持ち、筋肉1キログラムには約250グラムのタンパク質が含まれるため、単純計算では1,000 kcal程度となりますが、実際には筋肉合成のプロセス自体にもエネルギーが必要なため、より多くのカロリーが必要です。
適切なカロリーサープラス
筋肉を増やすための理想的なカロリーサープラスは、1日あたり200〜500 kcal程度とされています。身長170センチ、体重70キログラムで週3〜4回筋トレを行う男性の場合:
総消費カロリー:約2,592 kcal/日 目標摂取カロリー:2,792〜3,092 kcal/日(+200〜500 kcal)
月に0.5キログラムの筋肉を増やす場合、必要な余剰カロリーは: 2,000 kcal × 0.5kg = 1,000 kcal/月 1,000 kcal ÷ 30日 = 約33 kcal/日
しかし、これは理論上の最小値で、実際には筋肉だけでなく多少の脂肪も増えること、トレーニングによる消費カロリーの増加、個人差などを考慮すると、200〜300 kcal程度のサープラスが現実的です。
三大栄養素のバランス
カロリーだけでなく、タンパク質、炭水化物、脂質のバランスも重要です。
【タンパク質】 筋肉合成の材料となるタンパク質は、体重1キログラムあたり1.6〜2.2グラムの摂取が推奨されます。70キログラムの男性なら、1日に112〜154グラムが目安です。
タンパク質1グラムは約4 kcalなので、140グラム摂取する場合は560 kcalとなります。
【炭水化物】 筋トレのエネルギー源となり、筋グリコーゲンの補給にも必要です。総カロリーの45〜55%程度が目安で、2,900 kcalの食事なら1,305〜1,595 kcal、つまり326〜399グラム程度です。
炭水化物は筋肉合成を促進するインスリンの分泌にも関与するため、筋肥大には欠かせません。
【脂質】 ホルモン合成に必要で、総カロリーの20〜30%程度が適切です。2,900 kcalなら580〜870 kcal、つまり64〜97グラム程度です。
特にテストステロンなどの筋肉合成に関わるホルモンは、脂質から合成されるため、極端な低脂質食は避けるべきです。
カロリー過多による脂肪増加
過剰なカロリーサープラス(1日500 kcal以上)は、筋肉だけでなく脂肪の増加も促進します。脂肪1キログラムは約7,200 kcalに相当するため、1日500 kcalの過剰摂取を続けると:
500 kcal × 30日 = 15,000 kcal/月 15,000 kcal ÷ 7,200 kcal/kg = 約2.1 kg/月の脂肪増加
実際には、余剰カロリーの一部は筋肉合成や基礎代謝の増加にも使われるため、すべてが脂肪になるわけではありませんが、それでも月に1キログラム以上の脂肪が増える可能性があります。
理想的には、筋肉と脂肪の増加比率が3:1〜4:1程度になるようにカロリーをコントロールすることが望ましいとされています。月に0.5キログラムの筋肉を増やす場合、脂肪の増加は0.1〜0.2キログラム以内に抑えるのが理想です。
体重増加の個人差を決める要因
同じトレーニングプログラムと食事を行っても、筋肉の増加ペースには大きな個人差があります。その主な要因を見ていきましょう。
1. 遺伝的要因
筋肉の増えやすさには、遺伝が大きく関与しています。特に以下の要素が重要です:
- 筋繊維タイプの比率:速筋繊維(タイプII)の割合が多い人は筋肥大しやすい
- ミオスタチンのレベル:筋肉の成長を抑制するタンパク質で、これが少ない人は筋肉が増えやすい
- テストステロンの基礎レベル:筋肉合成を促進するホルモンの自然な分泌量
- インスリン感受性:栄養素を筋肉に取り込む効率
研究によれば、同じトレーニングを行っても、最も反応の良い人と悪い人では、筋肉の増加量に3〜4倍の差が出ることもあります。
2. 年齢
年齢も筋肉増加に大きく影響します。一般的に、20代〜30代前半が最も筋肉を増やしやすい時期で、それ以降は徐々に筋肉合成の効率が低下します。
これは、加齢とともにテストステロンなどのホルモン分泌が減少すること、筋肉合成のシグナル伝達が鈍くなること、タンパク質合成の効率が低下することなどが原因です。
40代では20代の約70〜80%、50代では約50〜60%程度の筋肥大反応になると言われています。ただし、適切なトレーニングと栄養管理により、高齢でも筋肉を増やすことは十分可能です。
3. トレーニング経験
前述の通り、初心者は最も速いペースで筋肉を増やせますが、経験を積むにつれてペースは遅くなります。これは体が刺激に慣れ、遺伝的な筋肉量の上限に近づいていくためです。
4. 生活習慣
- 睡眠:成長ホルモンの分泌は睡眠中に最も活発になります。睡眠不足は筋肉合成を大きく阻害します
- ストレス:慢性的なストレスはコルチゾールという筋肉分解を促進するホルモンの分泌を増やします
- アルコール:過度の飲酒はテストステロンの分泌を抑制し、筋肉合成を阻害します
5. 栄養状態
カロリーや三大栄養素だけでなく、ビタミンD、亜鉛、マグネシウムなどの微量栄養素も筋肉合成に重要な役割を果たします。
体重増加の評価方法
筋トレによる体重増加を正しく評価するには、体重だけでなく、複数の指標を組み合わせて見ることが重要です。
1. 体重の測定
毎日同じ時間帯(朝起きてトイレを済ませた後が理想的)、同じ条件で測定し、1週間の平均値を記録します。日々の変動に一喜一憂せず、週単位、月単位での傾向を見ることが大切です。
身長170センチの場合、標準体重は約63.6キログラム(BMI 22)ですが、筋肉質な体型を目指す場合、70〜75キログラム程度(BMI 24〜26)でも健康的な範囲内です。
2. 体脂肪率の測定
体組成計での測定は、正確性に限界があるものの、トレンドを見るには有用です。より正確な測定には、DEXA(二重エネルギーX線吸収測定法)やBodPod(空気置換法)などの専門的な機器が必要ですが、一般的には利用しにくいでしょう。
キャリパー(皮脂厚計)を使った測定も、慣れれば比較的正確な評価ができます。
3. 見た目と写真記録
同じ場所、同じ照明、同じ姿勢で定期的に写真を撮ることで、視覚的な変化を追跡できます。鏡で見る自分の印象よりも、写真の方が客観的な評価ができます。
4. 測定値の記録
胸囲、上腕囲、ウエスト、ヒップ、太もも周りなどを定期的に測定します。筋肉が増えれば、ウエスト以外の部位は太くなるはずです。
身長170センチ、体重70キログラムの標準的な男性の場合
- 胸囲:約95cm
- 上腕囲:約30cm(力こぶを作った状態)
- ウエスト:約78cm
- 太もも:約55cm
筋トレを1年継続すれば
- 胸囲:100〜105cm(+5〜10cm)
- 上腕囲:33〜36cm(+3〜6cm)
- ウエスト:76〜80cm(±2cm、腹筋の発達とウエストの引き締まりによる)
- 太もも:58〜62cm(+3〜7cm)
といった変化が期待できます。
5. パフォーマンスの向上
扱える重量や回数の増加も、筋肉の発達を示す重要な指標です。筋力と筋肉量は必ずしも比例しませんが、一般的には相関関係があります。
例えば、ベンチプレスで50キログラムしか挙げられなかった人が、6ヶ月後に70キログラムを挙げられるようになれば、確実に筋肉も増えていると言えるでしょう。
よくある誤解と注意点
誤解1:「筋トレをすると太る」
これは正確ではありません。筋トレによって体重が増えることはありますが、それは主に筋肉と水分の増加です。適切な食事管理を行えば、体脂肪を減らしながら筋肉を増やす「体組成の改善」も可能です。
ただし、筋肉を効率的に増やすには軽度のカロリーサープラスが有利であり、その過程で多少の脂肪も増える可能性はあります。しかし、その後のカットフェーズ(減量期)で脂肪を落とせば、最終的には引き締まった体になります。
誤解2:「体重が減らないとダイエット失敗」
体重が減らなくても、体脂肪が減って筋肉が増えていれば、それは成功です。むしろ、急激な体重減少は筋肉も一緒に減っている可能性が高く、代謝の低下やリバウンドのリスクを高めます。
身長170センチ、体重70キログラムで体脂肪率20%の人が、3ヶ月後も70キログラムのままでも、体脂肪率が15%に減っていれば:
- 脂肪量:14kg → 10.5kg(-3.5kg)
- 除脂肪量:56kg → 59.5kg(+3.5kg)
という大きな改善が起きています。
誤解3:「女性は筋トレすると太くなる」
女性は男性に比べてテストステロンの分泌量が約1/10〜1/20程度しかないため、男性と同じようには筋肉がつきません。適度な筋トレでは、ボディビルダーのような筋肉質な体にはならず、むしろ引き締まったメリハリのある体型になります。
女性の場合、筋トレ初年度で増やせる筋肉は年間3〜6キログラム程度で、男性の半分程度です。
注意点1:過度なカロリーサープラスは避ける
「バルクアップ」の名目で過剰にカロリーを摂取すると、筋肉よりも脂肪の増加が大きくなってしまいます。増える体重の内訳が、筋肉:脂肪=1:1や、それ以下になってしまうと、後の減量が大変になります。
月の体重増加が1キログラムを超える場合は、カロリー摂取を見直すべきサインです。
注意点2:急激な体重変動に注意
1週間で2キログラム以上の急激な体重増加は、主に水分や消化物の増加である可能性が高いです。一方、1週間で2キログラム以上の急激な体重減少は、筋肉も一緒に減っている可能性があります。
健康的な体重変動のペースは、増量期でも週に0.25〜0.5キログラム、減量期でも週に0.5〜1キログラム程度が適切です。
注意点3:体重増加が止まった時
初めは順調に体重が増えていたのに、ある時点で増えなくなることがあります。これは体が新しい体重に適応し、消費カロリーも増えたためです。
この場合、さらなる筋肉増加を目指すなら、トレーニング強度を上げるか、摂取カロリーを少し増やす必要があります。ただし、既に十分な筋肉がついている場合は、無理に増やそうとせず、現状維持や体組成の改善に焦点を移すのも一つの選択です。
まとめ
筋トレによる体重増加は、多くの場合、体が良い方向に変化している証拠です。身長170センチ、体重70キログラムの標準的な男性を基準に、本記事で解説した主なポイントをまとめます。
筋肉と脂肪の違い
筋肉の密度(1.1g/cm³)は脂肪の密度(0.9g/cm³)よりも約20%高く、同じ重さでも筋肉の方が体積は約22%小さくなります。これが、体重が変わらなくても見た目が引き締まる理由です。脂肪1キログラムを筋肉1キログラムに置き換えれば、体重は同じでも体積は約200cm³減少します。
体重増加のメカニズム
筋トレによる体重増加の主な要因は:
- 筋肉量の増加:筋繊維そのものの肥大
- グリコーゲンと水分の貯蔵:グリコーゲン1グラムに3〜4グラムの水分が結合
- 炎症反応による一時的な水分貯留:特にトレーニング初期に顕著
- 食事量の増加に伴うカロリーサープラス:筋肉だけでなく多少の脂肪も増える可能性
体内水分量
成人男性の体重の約60%は水分で、70キログラムの男性なら約42キログラムが水分です。筋肉組織の約75%も水分であるため、筋肉1キログラムの増加には、実質的なタンパク質約250グラムと、水分約750グラムが含まれます。日々の水分変動により、体重は1〜2キログラム程度簡単に変動するため、1週間の平均値で評価することが重要です。
現実的な筋肉増加ペース
- 初心者(1年目):月に0.5〜1kg、年間6〜12kg(理想的条件下)
- 2年目:月に0.25〜0.5kg、年間3〜6kg
- 3年目以降:年間2〜3kg程度に減速
- 5年目以降:年間1kg程度の維持が目標
身長170センチ、体重70キログラムの男性が1年間筋トレを継続した場合、筋肉が6〜10キログラム増加し、グリコーゲンと水分で約1キログラム、適切な食事管理により脂肪が2〜3キログラム減少すれば、実際の体重は4〜8キログラム増加し、74〜78キログラム程度になると予想されます。
カロリーと栄養
筋肉1キログラムを合成するには約1,700〜2,500 kcalの余剰カロリーが必要です。理想的なカロリーサープラスは1日200〜500 kcal程度で、70キログラムの男性が週3〜4回筋トレを行う場合、総消費カロリーは約2,600 kcalなので、2,800〜3,100 kcalの摂取が目安となります。
栄養素のバランスは:
- タンパク質:体重1kgあたり1.6〜2.2g(70kgなら112〜154g/日)
- 炭水化物:総カロリーの45〜55%(約330〜400g/日)
- 脂質:総カロリーの20〜30%(約65〜95g/日)
正しい評価方法
体重だけでなく、以下を総合的に評価することが重要です:
- 体重(週平均値)
- 体脂肪率
- 見た目の変化(定期的な写真記録)
- 各部位の測定値(胸囲、上腕囲、ウエスト、太もも周りなど)
- トレーニングパフォーマンス(扱える重量や回数)
最後に
筋トレによる体重増加は、必ずしも悪いことではありません。むしろ、適切な増加は筋肉が増えている証拠です。体重という数字だけに囚われず、体組成の変化、見た目の改善、パフォーマンスの向上を総合的に評価しましょう。
身長170センチ、体重70キログラムという標準的な体格から、筋肉質で引き締まった75キログラムになるのと、運動不足で脂肪が多い75キログラムになるのでは、見た目も健康状態も大きく異なります。
重要なのは、体重計の数字ではなく、鏡に映る自分の姿、服のサイズ感、日常生活での動きやすさ、そして自分自身が感じる体の変化です。適切なトレーニング、栄養管理、休息を継続することで、理想の体を作り上げていきましょう。
体重が増えても、それが筋肉と水分による健康的な増加であれば、それは成功への道のりの一部です。焦らず、長期的な視点で体づくりに取り組むことが、最終的な成功につながります。