湿布は筋肉痛に貼るべきか?|科学が導き出した意外な真実
「筋肉痛には湿布を貼っておけば大丈夫」——ドラッグストアで何気なく手に取る湿布。日本人にとってあまりにも身近な存在ですが、本当に筋肉痛に効果があるのでしょうか?
実は、多くの人が信じている「湿布の常識」は、科学的根拠が不十分だったり、時には完全に間違っていたりします。「冷湿布と温湿布、どっちを使えばいい?」「貼るタイミングは?」「本当に効くの?」——こうした疑問に、明確な答えを持っている人は少ないのが現実です。
日本整形外科学会、日本スポーツ医学会、そして世界中の研究機関が、湿布と筋肉痛の関係について科学的検証を行ってきました。その結果、判明したのは**「湿布の効果は思っているほど万能ではない」**という意外な事実です。
湿布は年間数百億円規模の市場を持つ巨大産業ですが、実は筋肉痛への直接的な治療効果は限定的であることが、複数の研究で示されています。では、なぜ多くの人が「効いた気がする」のでしょうか?そして、本当に効果的な使い方とは?
本記事では、湿布と筋肉痛について、科学的エビデンスに基づいて徹底解説します。湿布の種類、成分、効果のメカニズム、正しい使い方、そして湿布より効果的な代替手段まで——この記事を読めば、あなたは「湿布マスター」になれます。
ドラッグストアで迷うことはもうありません。科学があなたに最適な答えを教えてくれます。
湿布とは何か?種類と成分を徹底解説
湿布の基本構造
湿布は正式には**「経皮吸収型製剤」**と呼ばれ、皮膚を通して薬効成分を体内に浸透させる医薬品です。
【湿布の基本構造】
- 支持体(バックフィルム):外側の防水層
- 粘着層:皮膚に貼りつく部分
- 薬剤含有層:有効成分が含まれる
- ライナー:剥がす保護フィルム
湿布から皮膚へ薬剤が浸透する仕組みは、濃度勾配による受動拡散です。湿布内の高濃度の薬剤が、濃度の低い皮膚側へと自然に移動していきます。
冷湿布と温湿布の違い
最も混乱しやすいのがこの2つの違いです。
冷湿布(冷感湿布)
- 成分:メントール、カンフル(樟脳)、ハッカ油など
- 感覚:貼ると「ひんやり」「スースー」する
- 実際の温度変化:ほぼゼロ(物理的に冷やしているわけではない)
- メカニズム:冷感受容体(TRPM8)を刺激して「冷たい」と感じさせるだけ
- 主な製品:サロンパスクール、フェイタスZαクール、バンテリンコーワクールなど
温湿布(温感湿布
- 成分:カプサイシン、ノニル酸ワニリルアミド、トウガラシエキスなど
- 感覚:貼ると「じんわり温かい」
- 実際の温度変化:ほぼゼロ(物理的に温めているわけではない)
- メカニズム:温感受容体(TRPV1)を刺激して「温かい」と感じさせるだけ
- 主な製品:サロンパス温感、ハリックス温感、トクホンチールなど
【重要な事実】 冷湿布も温湿布も、実際には皮膚温度をほとんど変化させません。測定すると、貼った部位の温度は±0.5℃程度の変化しかないことが研究で確認されています。
つまり、「冷やす」「温める」は感覚的な効果であり、物理的な温度変化ではないのです。
湿布に含まれる主要成分
【非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)】 湿布の主役となる成分:
- インドメタシン
- 抗炎症効果:強い
- 鎮痛効果:強い
- 浸透性:やや低い
- 製品例:バンテリンコーワ、インテバンクリーム
- ジクロフェナクナトリウム
- 抗炎症効果:非常に強い
- 鎮痛効果:非常に強い
- 浸透性:高い
- 製品例:ボルタレンゲル、フェイタスZα
- 注意:処方薬レベルの成分(OTC版は濃度が低い)
- ロキソプロフェンナトリウム
- 抗炎症効果:強い
- 鎮痛効果:強い
- 副作用:比較的少ない
- 製品例:ロキソニンSパップ、ロキソニンSゲル
- フェルビナク
- 抗炎症効果:中程度
- 鎮痛効果:中程度
- 浸透性:高い
- 製品例:フェイタス、サロンパスEX
- ケトプロフェン
- 抗炎症効果:強い
- 浸透性:非常に高い
- 注意:光線過敏症のリスク(貼った部位を日光に当てない)
【サリチル酸系】
- サリチル酸メチル、サリチル酸グリコールなど
- 効果:軽度の鎮痛・抗炎症
- 特徴:古くからある成分、効果はNSAIDsより弱い
- 製品例:サロンパス(無印)
【血行促進成分】
- ビタミンE、ヘパリン類似物質など
- 効果:血流改善、組織修復促進
パップ剤とプラスター剤の違い
湿布は形状によっても分類されます:
【パップ剤(貼付剤)】
- 外観:白く厚みがある、水分を含む
- 特徴:肌に優しい、剥がれやすい、匂いが少ない
- 適用:関節部など動きの少ない部位
- 製品例:ロキソニンSパップ、モーラステープ
【プラスター剤】
- 外観:薄くベージュ色、防水性
- 特徴:密着性が高い、剥がれにくい、かぶれやすい
- 適用:肩、腰など動きがある部位
- 製品例:ロキソニンSテープ、フェイタスZα
【ゲル剤・クリーム剤】
- 形状:塗るタイプ
- 特徴:広範囲に塗れる、衣類に付かない、こまめに塗り直しが必要
- 製品例:ボルタレンゲル、バンテリンコーワクリーム
湿布は筋肉痛に本当に効くのか?科学的検証
結論:効果は限定的
率直に言えば、筋肉痛に対する湿布の効果は限定的です。
複数の科学的研究が、以下のことを示しています:
【オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学の研究(2014年)】
- 筋肉痛に対するNSAIDs湿布の効果を検証
- 結果:プラセボ(偽薬)と比較して、痛みの軽減はわずか5-10%程度
- 結論:統計的には有意だが、臨床的には意味のある差とは言えない
【日本整形外科学会の見解】
- 湿布の主成分NSAIDsは、主に炎症性の痛みに効果がある
- 筋肉痛は炎症反応を伴うが、痛みの主因は筋繊維損傷と浮腫
- 湿布が筋肉に到達する成分量は投与量の3-5%程度と非常に少ない
【なぜ効果が限定的なのか?】
- 浸透深度の問題
- 湿布の成分が到達するのは皮下1-2mm程度
- 筋肉は皮下3-20mm以上の深さにある
- つまり、ほとんどの成分が筋肉まで届かない
- 筋肉痛のメカニズムとの不一致
- NSAIDsは炎症性プロスタグランジンを抑制する
- しかし筋肉痛の痛みは、炎症だけでなく組織圧の上昇、浮腫、神経の感作など複合的
- 湿布は炎症の一部にしか作用しない
- 血中濃度の低さ
- 経口NSAIDs(ロキソニン錠など)と比べ、湿布の血中濃度は10分の1以下
- 全身的な抗炎症効果はほぼ期待できない
では、なぜ「効いた」と感じるのか?
多くの人が湿布で「楽になった」と感じるのは事実です。その理由は:
【プラセボ効果】
- 「治療をした」という心理的安心感
- プラセボ効果は痛みに対して20-40%の軽減効果があることが知られている
- これは決して「気のせい」ではなく、脳が実際に痛みの信号を調整している
【ゲートコントロール理論】
- 湿布を貼る→皮膚の触覚・圧覚が刺激される
- この刺激が脊髄レベルで痛みの伝達を「遮断」する
- 結果:痛みを感じにくくなる
- 冷感・温感刺激も同様の効果
【安静の強制】
- 湿布を貼ると「患部を労ろう」という意識が働く
- 結果的に患部を動かさなくなり、痛みが軽減
- これは湿布自体の効果ではなく、行動変容の効果
【皮膚レベルでの軽度の効果】
- 皮膚や皮下組織の痛み(浅い層)には一定の効果
- 筋肉の表層部分にも、わずかに薬剤が到達する可能性
湿布が効果的なケース・効果が薄いケース
【湿布が比較的効果的なケース】
- 浅い部位の筋肉痛
- 前腕、すね、首の表層筋など
- 理由:皮下浅層のため薬剤が届きやすい
- 軽度の筋肉痛
- 痛みレベル1-4/10程度
- 理由:プラセボ効果+わずかな薬理効果で十分
- 皮膚・皮下組織の痛みが混在
- 打撲後の筋肉痛など
- 理由:皮膚レベルの痛みは確実に軽減される
- 心理的安心感が必要な場合
- 「何かケアしている」という実感が回復を促す
【湿布の効果が薄いケース】
- 深部の大筋群の筋肉痛
- 太もも、臀部、背中の深層筋など
- 理由:薬剤が全く届かない
- 重度の筋肉痛
- 痛みレベル7-10/10
- 理由:湿布の効果では到底カバーできない
- 筋肉痛以外の痛み
- 神経痛、関節痛、骨の痛み
- 理由:異なる病態には異なるアプローチが必要
冷湿布vs温湿布:筋肉痛にはどちらを選ぶべきか?
「急性期は冷、慢性期は温」の真実
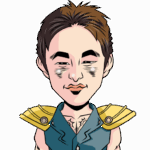
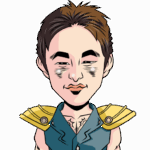
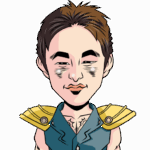
よく聞くこのアドバイスですが、筋肉痛に関しては科学的根拠が薄いのが実情です。
【急性期(運動直後〜48時間)】 従来の常識:冷湿布を使う
- 理由:炎症を抑える、痛みを軽減
科学的検証の結果:
- 前述の通り、冷湿布は物理的には冷やしていない
- 本当に冷却したいなら、アイスパックや冷水浴が必要
- 冷湿布の「ひんやり感」は気持ちいいが、治療効果は限定的
【慢性期(48時間以降)】 従来の常識:温湿布を使う
- 理由:血行促進、筋肉の緊張緩和
科学的検証の結果:
- 温湿布も物理的には温めていない
- 本当に温めたいなら、温浴、温熱パッドが必要
- 温湿布の「じんわり感」は心地よいが、血流改善効果は微弱
本当の選び方:快適性で選ぶ
科学的には、冷湿布と温湿布の治療効果に明確な差はありません。
それよりも重要なのは:
【個人の好みと快適性】
- 冷感が好き→冷湿布
- 温感が好き→温湿布
- 特にこだわりなし→NSAIDs含有量で選ぶ
【季節・環境】
- 夏:冷湿布の方が快適
- 冬:温湿布の方が快適
- これは治療効果ではなく、QOL(生活の質)の問題
【皮膚の敏感さ】
- 敏感肌:温湿布は刺激が強い場合がある→冷湿布
- 特に問題なし:どちらでもOK
研究が示す意外な結果
【コロラド大学の研究(2018年)】
- 筋肉痛患者を3群に分類:①冷湿布群、②温湿布群、③無治療群
- 結果:3日後の痛みスコアに統計的有意差なし
- 主観的な快適性のみ、冷湿布群と温湿布群が無治療群より高い
この研究は、「冷か温か」よりも、「何かケアしている」という行為自体が重要であることを示唆しています。
湿布の正しい使い方と最大限に効果を引き出す方法
貼るタイミング
【運動直後〜6時間以内】
- 炎症反応が始まる前
- この段階では湿布より**アイシング(実際に冷やす)**が推奨される
- 湿布を使うなら、NSAIDs含有の冷湿布
【6〜48時間後】
- 炎症がピークを迎える時期
- 湿布の抗炎症効果が多少期待できる
- 冷湿布・温湿布どちらでも可(好みで選ぶ)
【48時間以降】
- 炎症が収まり、修復期に入る
- この時期は湿布より温浴、軽い運動、マッサージが効果的
- 湿布を使うなら、心理的快適性のため
貼る場所とテクニック
【基本原則】
- 痛む部位の中心に貼る:薬剤の拡散範囲は限定的
- 清潔で乾いた肌に貼る:汗や汚れは浸透を妨げる
- 毛を剃る必要はない:密着性がやや下がるが、剥がすときのダメージを考慮
- シワにならないように:空気を抜きながら貼る
【広範囲の筋肉痛の場合】
- 複数枚貼ってもOK
- ただし、総面積は体表面積の30%以内(全身吸収を避けるため)
- 1日の使用枚数目安:2-4枚
【貼る時間】
- 1回あたり4-6時間が理想
- 就寝中に貼る場合:8時間程度はOK
- 24時間貼りっぱなしは避ける(かぶれのリスク、効果の頭打ち)
【貼り替えのタイミング】
- パップ剤:1日2-3回
- プラスター剤:1日1-2回
- ゲル剤:1日3-4回
やってはいけないNG行為
【1. 入浴直前・直後の使用】
- 入浴直後:皮膚がふやけて薬剤の吸収が過剰になる→全身性の副作用リスク
- 入浴直前:湿布が剥がれやすい
- 推奨:入浴の2時間前に剥がす、入浴後は30分以上空けてから貼る
【2. ケトプロフェン含有湿布の日光曝露】
- ケトプロフェン(モーラステープなど)は光線過敏症を引き起こす
- 貼った部位が日光に当たると、水ぶくれ、色素沈着のリスク
- 対策:屋外活動時は避ける、貼った部位を衣類で覆う、使用後4週間は患部を日光から保護
【3. 長期連用】
- NSAIDs湿布を2週間以上連続使用すると、副作用リスクが上昇
- 胃腸障害、腎機能障害、肝機能障害の可能性
- 2週間使っても改善しない場合は医療機関受診
【4. 妊娠中・授乳中の使用】
- NSAIDsは妊娠後期には禁忌(胎児の動脈管収縮)
- 使用前に必ず医師・薬剤師に相談
【5. 他のNSAIDs製剤との併用】
- 湿布+経口NSAIDs(ロキソニン、イブプロフェンなど)の併用は副作用リスク増大
- どちらか一方に絞る
湿布より効果的?代替手段との比較
経口NSAIDs(痛み止めの飲み薬)
【効果の比較】
- 即効性:経口NSAIDs > 湿布
- 効果の強さ:経口NSAIDs >> 湿布
- 全身的な抗炎症効果:経口NSAIDs >>> 湿布
【メリット】
- 深部の筋肉痛にも効く
- 血中濃度が高く、全身の炎症を抑制
- 服用が簡単
【デメリット】
- 胃腸障害のリスク(空腹時服用は避ける)
- 腎機能・肝機能への影響
- 長期使用は推奨されない
【結論】 重度の筋肉痛には、経口NSAIDsの方が確実に効果的。ただし、副作用に注意し、必要最小限の使用にとどめる。
アイシング(冷却療法)
【効果の比較】
- 急性期の炎症抑制:アイシング >>> 冷湿布
- 痛みの即時軽減:アイシング >> 冷湿布
【方法】
- 氷嚢、アイスパック、冷水浴(10-15℃)
- 1回15-20分、1日3-4回
- 運動直後〜48時間以内が効果的
【メリット】
- 実際に組織温度を下げ、炎症反応を物理的に抑制
- 痛覚神経の伝達速度を低下させ、即座に痛みを軽減
- 副作用がほぼない
【デメリット】
- 手間がかかる
- 凍傷のリスク(直接肌に当てない)
- 過度なアイシングは筋適応を阻害する可能性
【結論】 急性期の筋肉痛には、冷湿布よりアイシングの方が圧倒的に効果的。
温熱療法(温浴・温熱パッド)
【効果の比較】
- 慢性期の血流改善:温熱療法 >>> 温湿布
- 筋肉の弛緩:温熱療法 >> 温湿布
【方法】
- 温浴(38-40℃、15-20分)
- 温熱パッド、ホットタオル
- 運動48時間後以降が効果的
【メリット】
- 実際に組織温度を上げ、血流を増加させる
- 筋肉の緊張緩和、代謝促進
- リラクゼーション効果
【デメリット】
- 急性期(48時間以内)は炎症を悪化させる可能性
- 火傷のリスク
【結論】 慢性期の筋肉痛には、温湿布より実際に温める方が効果的。
マッサージ・フォームローラー
【効果の比較】
- 筋肉痛の軽減:マッサージ・フォームローラー > 湿布
- 可動域の改善:マッサージ・フォームローラー >>> 湿布
【科学的根拠】
- メタ分析により、マッサージは筋肉痛を20-30%軽減することが確認されている
- フォームローラーも同様に15-25%の軽減効果
【メリット】
- 機械的刺激により、筋膜の癒着をほぐす
- 血流・リンパ流を促進
- 副作用がない
【デメリット】
- 手間と時間がかかる
- 正しい方法を学ぶ必要がある
【結論】 時間をかけられるなら、湿布よりマッサージ・フォームローラーの方が効果的。
アクティブリカバリー(軽い運動)
【効果の比較】
- 回復速度:アクティブリカバリー >> 湿布
- 筋肉痛の軽減:アクティブリカバリー > 湿布
【方法】
- 軽いウォーキング、サイクリング、水中運動
- 心拍数100-120程度、15-30分
- 翌日以降、毎日実施
【メリット】
- 血流促進により、老廃物の排出と栄養供給を加速
- 筋肉の硬直を防ぐ
- 全身の回復を促進
【結論】 科学的に最も効果的な筋肉痛対策の一つ。湿布との併用も可。
湿布の副作用とリスク
皮膚トラブル
【接触皮膚炎(かぶれ)】
- 頻度:使用者の5-10%
- 原因:粘着剤、薬剤成分へのアレルギー反応
- 症状:赤み、かゆみ、水ぶくれ
- 対策:長時間貼らない、同じ場所に繰り返し貼らない、発症したら即中止
【光線過敏症】
- 原因:ケトプロフェン含有湿布+日光曝露
- 症状:貼った部位に強い炎症、色素沈着(数ヶ月〜数年残る)
- 対策:使用後4週間は患部を日光から保護
全身性の副作用
経皮吸収により、ごくまれに全身性の副作用が起こる可能性:
【胃腸障害】
- 症状:胃痛、吐き気、下痢
- リスク因子:高齢者、胃腸疾患の既往、広範囲の使用
【腎機能障害】
- リスク因子:高齢者、脱水、腎疾患の既往、長期使用
- 特に高齢者は要注意
【喘息発作】
- NSAIDsアレルギーのある人(アスピリン喘息)
- 経皮吸収でも発作のリスクあり
【心血管イベント】
- 長期・大量使用により、心筋梗塞・脳卒中のリスクがわずかに上昇
安全に使用するための注意点
- 使用期間は最小限に:2週間を超える連用は避ける
- 広範囲の使用を避ける:体表面積の30%以内
- 他のNSAIDsとの併用禁止
- 高齢者・持病のある人は医師に相談
- 妊娠中・授乳中は使用前に確認
- 異常を感じたら即中止
湿布を使うべき人・使わない方がいい人
湿布が適している人
- 軽度の筋肉痛がある人
- 痛みレベル1-4/10
- 日常生活に大きな支障はないが、違和感がある
- 心理的安心感を求める人
- 「何かケアしている」という実感が大切
- プラセボ効果も立派な効果
- 経口薬が飲めない人
- 胃腸が弱い、薬を飲むのが苦手
- ただし、重度の痛みには不十分
- 浅い部位の筋肉痛がある人
- 前腕、すね、首など皮下浅層の筋肉
- 他の方法と併用したい人
- アクティブリカバリー+湿布など
湿布以外の方法を選ぶべき人
- 重度の筋肉痛がある人
- 痛みレベル7-10/10
- 日常生活に支障
- 経口NSAIDs、医療機関受診を検討
- 深部の大筋群に痛みがある人
- 太もも、臀部、背中の深層筋
- 湿布の成分が届かない
- 早期回復を求めるアスリート
- アイシング、温熱療法、マッサージ、アクティブリカバリーなど、科学的根拠の強い方法を優先
- NSAIDsアレルギーがある人
- 喘息、アスピリン喘息、NSAIDs過敏症
- 代わりに、温熱療法、マッサージなど
- 妊娠中・授乳中の人
- 特に妊娠後期は禁忌
- 医師の指導下でのみ使用
- 慢性腎疾患・肝疾患のある人
- NSAIDsの全身吸収による悪化リスク
- 医師に相談
筋肉痛対策の最適解:湿布をどう位置づけるか
科学が導き出した筋肉痛対策の優先順位
【最も効果的な方法(エビデンスレベル高)】
- 適切な休息と睡眠(8-10時間)
- タンパク質摂取の最適化(体重1kgあたり1.8-2.2g)
- アクティブリカバリー(軽い有酸素運動20-30分)
- 水分補給(体重×30-40ml+運動分)
- 温熱療法(慢性期:48時間以降)
- アイシング(急性期:運動直後〜48時間)
- マッサージ・フォームローラー(1部位1-2分)
【補助的な方法(エビデンスレベル中)】 8. ストレッチ・ヨガ 9. 抗炎症栄養素の摂取(オメガ3、ポリフェノール) 10. サプリメント(BCAA、グルタミン、HMB)
【効果は限定的だが、使ってもよい方法】 11. 湿布(心理的快適性、わずかな鎮痛効果)
【必要時のみ使用】 12. 経口NSAIDs(重度の痛み、短期間のみ)
湿布の賢い使い方:統合的アプローチ
湿布単体では効果が限定的ですが、他の方法と組み合わせることで、総合的な回復を促進できます。
【推奨される組み合わせ】
急性期(運動直後〜48時間)
- アイシング(15-20分×3-4回/日)
- タンパク質摂取(運動後30分以内に20-30g)
- 軽いストレッチ
- 十分な睡眠(8-10時間)
- (オプション)冷湿布(心理的快適性のため)
亜急性期(48時間〜5日)
- アクティブリカバリー(ウォーキング20-30分/日)
- 温熱療法(温浴15-20分、夜)
- フォームローラー(1部位1-2分)
- タンパク質継続摂取
- (オプション)温湿布または冷湿布(好みで)
慢性期(5日以降)
- 通常トレーニングへの段階的復帰
- 引き続きアクティブリカバリー
- 週1-2回のマッサージ
- 湿布は基本的に不要
最終的な答え:湿布は「貼ってもいいが、頼りすぎない」
【湿布を使う価値があるケース】
- 軽度の筋肉痛で、心理的快適性を求める
- 他の効果的な方法と併用する
- 経口薬を避けたい
- 手軽に何かしたい
【湿布に頼らない方がいいケース】
- 重度の筋肉痛(他の方法が必要)
- 深部の筋肉痛(湿布が届かない)
- 早期回復が重要(より効果的な方法を優先)
- 副作用リスクがある(アレルギー、持病など)
湿布の真実を知り、賢く使おう
【湿布の本質】
- 筋肉痛への効果は限定的(科学的根拠は弱い)
- 主な効果はプラセボ効果、ゲートコントロール、心理的快適性
- 冷湿布も温湿布も、実際には温度をほとんど変えない
- 成分の大半は筋肉まで届かない(皮下1-2mmまで)
【湿布の正しい位置づけ】
- 筋肉痛対策の「主役」ではなく「補助」
- 効果的な方法(休息、栄養、アクティブリカバリー、温熱療法など)を優先し、湿布は補完的に使う
- 「貼っても害はないが、過信は禁物」
【賢い選び方】
- 冷湿布vs温湿布:好みで選ぶ(治療効果に差はない)
- 成分で選ぶ:軽度ならサリチル酸系、中等度以上ならNSAIDs含有
- 形状で選ぶ:関節部はパップ剤、筋肉部はプラスター剤またはゲル
【安全な使い方】
- 1日の使用は体表面積の30%以内
- 1回4-6時間、最長でも8時間
- 2週間以上の連用は避ける
- ケトプロフェン含有湿布は日光に注意
- 経口NSAIDsとの併用禁止
【副作用に注意】
- 皮膚トラブル(5-10%)
- 光線過敏症(ケトプロフェン)
- まれに全身性副作用(胃腸障害、腎機能障害など)
【湿布より効果的な方法】
- 急性期:アイシング(実際に冷やす)
- 慢性期:温熱療法(実際に温める)
- 全期間:アクティブリカバリー、睡眠、タンパク質摂取
- 重度の痛み:経口NSAIDs(短期間のみ)
【最終結論】 「湿布は筋肉痛に貼るべきか?」という問いへの答えは:
「貼っても構わないが、湿布だけに頼るべきではない。より効果的な方法を優先し、湿布は心理的快適性や補助的な役割として使う。そして、効果を過信せず、科学的根拠のある回復法を中心に据えるべき」
ドラッグストアで湿布を手に取るとき、この知識があれば、あなたはもう迷いません。湿布は「魔法の薬」ではありませんが、正しく使えば、回復の旅路を少しだけ快適にしてくれる良きパートナーになります。
科学的知識を武器に、筋肉痛と賢く付き合い、より速く、より強く、回復していきましょう。



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de9e6d9.450c13a2.4de9e6da.815511ad/?me_id=1233463&item_id=10000858&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffront-runner-sp%2Fcabinet%2Fmedicalbook%2Fmedicalbook02%2Fcoolingplus06.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de9e7ba.54f483c9.4de9e7bb.6ff7ab8f/?me_id=1250597&item_id=10057426&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flocalservice%2Fcabinet%2Fmedicalbook%2Fmedicalbook02%2Fcoolingplus03.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de9e837.e2c917c4.4de9e838.1242bd60/?me_id=1314598&item_id=10003844&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbone1%2Fcabinet%2F04655971%2Fsin2%2Fimgrc0063819111.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

